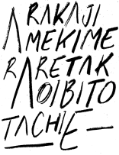MUSIC VIDEO
LISTEN
NOVEL
火花
「アンタが見たのは『クストゥデス』。でもそれは偉い大人たちの言葉で、アタシは『あいつら』だし、最近は『ダム・サーファー』ってのがオシャレみたい。歴史をたどると天使とか悪魔とか死神とか、国や年代によって呼び方は様々って感じだね」
「クストゥデス?」
青の口から発された聴き慣れない言葉を繰り返す。デスという語尾が死神を連想させた。
「クゥィス・クストゥディエト・イプソース・クストゥデス」
何語かわからないが流暢な発音だった。
「イタリア語?」当てずっぽうで言う。
「惜しいね。これは古いラテン語でさ。『誰が見守る者を見守るのか』って意味なの」
「なんか早口言葉みたいだったけど」話がどう繋がるのかわからない。
「ローマ時代のユウェナーリスって詩人が残したフレーズで、私たちのテーマだね。クストゥデスは『見守る者』って意味。アタシたちは身守る者を見守ってんの」
寝床を求めてウミネコが飛来し、暗い海に着水した。心がざわめく。
「あなたが、なんとかデスってのを見守ってて、なんとかデスは何をしてんの」
「人間を見守ってるってことになってる、一応はね」
「もしかして、地底人とか爬虫類人とか、そういう話?」
輪河鈴が担当したオカルトサイトにそんな記事があった。
「日常生活の違和感って結構、あいつらが絡んでるし、最近はアブネーのも多いから、あながち間違いではないかもね」
「危ない?」私は青の言葉を繰り返す。
「あいつらは肉体を持たないから、直接的には何もできない。『精神寄生体』って言えばわかるかな。こっそり人間の心に侵入して、宿主をジャンプしながら永遠に生きてんの」
「古いSFでそんなのがあったけど」
身近な人々がエイリアンに乗っ取られていく。社会に馴染めない輪河鈴が自身を重ねた映画を思い出す。
「アタシにとってはスーパーハイビジョンの現実だよ」青はパチンと指を鳴らす。
「それってウィルスみたいなもの?」私は顎のマスクを意識した。
「似てるけど違うね。あいつら自体は増えないから」
荒唐無稽な話だった。もし私が悪夢を見ていなければ不思議少女のファンタジーとして聞き流しただろう。
「なら、何をしてるわけ?」
「クストゥデス一体につき、最大百人程度の宿主をリザーブしてて、半日から一日の周期で宿を移動してんの」
「移動って?」
「宿主が眠るとアクティブな別の宿主へ飛ぶ。あいつら、夢が天敵なの。知ってる? 夢ってさ、心の抗体反応なんだって。起きてる時に入ってきた精神に有害な情報を、シュレーダーみたく噛み砕く。深層意識へ入っちゃうと取り除くのが困難で、それが原因で心の病気になっちゃうからさ。人間はその時、飛び散る破片を夢だと思ってるんだって」
そういえば、事件以降、私は夢を見てない。
「なんとかデスも異物として排除されるってこと?」
「うん。人間の生活リズムがバラバラになったおかげで、あいつら活動範囲を一気に広げたけど、電気がない時代はみんな同じ時間に寝るじゃん? だから、不眠症の人に憑いてたみたい」
かつてヴェネツィアに存在した、眠れない一族の記事が脳裏をよぎる。
「その、なんとかデスってのは、いつから存在するの?」
「人類の歴史が始まった頃じゃないかって言われてる。そういや、『精神寄生体に取り憑かれた猿が、人間へと進化した』って唱えた作家もいたみたい。ドラッグ大好きでさ。ウィリアムテルごっこで間違って妻を撃ち殺しちゃったんだけど」
編集長が好きなアメリカの作家だった。青は秘密を共有できた嬉しさからかどんどんお喋りになる。その姿が編集長と重なった。私は無言で続きを促す。
「ドラッグにはあいつらを活性化させるものと、抑制するものに大別されんの。何日も眠らないクスリは精神的抗体が弱まって寄ってくるし、トランキライザーは黙らせる効果が期待できる」
「薬が効くんだ」暗い海を見ながら、安定剤を飲んだ夜を思い出す。潮が満ちるように増す動揺を抑えて私は頷く。
「長くなるならさ、編集長が心配してるだろうし電話しとかない?」私の提案に、青は三日月のように瞳を釣り上げた。
「アタシらが今話してること、国家的トップシークレットだから。携帯なんか電源入れた瞬間、総務部に筒抜けじゃん。だから電話は駐車場に隠してきたし、こんな汚ぇとこで話してんのも、カメラの心配がないからなんだよ」
「ポケットに携帯持ってなかった?」私は先ほど膨らみを感じた青のスカートを指さす。
「あ、これ?」
青はバックルを開き、手のひらサイズの木片を取り出した。江戸時代のカマボコ板と言われたら誰もがそう思うだろう。女子高生には似つかない年季の入ったアイテムだった。
「これはうちに代々伝わるお守りで、五百年前、神の木から作ったの。なんだよ、笑うなよ」
よく見るとマジックで「iPhone」と書かれていて吹き出してしまった。
「いや、アップル製なのかと」
「リビングに置き忘れてお風呂入ってる間にタコ社長が落書きしたんだよ。商売道具にふざけやがって」
いかにも編集長がやりそうな悪戯だ。
「商売ってアナタ女子高生でしょ?」
「それは世を偲ぶ仮の姿。アタシの家系は沖縄で代々『イミミ』つって、夢の中に入って村人を治療してるんだ」
「へー。それがなんでまた東京に?」
「アンタさ」青は口を尖らせる。「うわ!とかすごい!とか嘘でもないわけ。張り合いないんだけど」
コロコロと表情を変える姿は普通の女子高校生だ。
「一度にいろいろ聞きすぎて、驚くのも疲れちゃって」
本当は違った。何かどうしようもないことがすでに起きており、それに気づかないよう振る舞うのが難しくなってきたという感覚だった。
「何の因果か、公安総務部に拾われて、今は見守り隊やってんの。これは夢を操る呪具」
青は大事そうに板をポケットにしまった。
「クストゥデスだっけ、そいつは悪者なの?」
「ニュートラルだね」青はふんと鼻を鳴らす。「ヒトの精神に取り憑いてるから基本、人間と同じ。大したことはしないよ。クストゥデスって名前の通り、ただ見守ってるだけ。ぼーっと人の一生を眺めてる。多分、ポテチ食いながら退屈なドラマ見る日曜が永遠に続く感じ?」
「それは幸せなのかな」悪くないような気もした。
「人に干渉しないのが大半だから満足してんじゃない? けどたまに変なのがいて、宿主に話しかけんの。『ウィスパー』って呼ばれてるんだけどさ。神とか電波とか狐とか、声聞こえちゃう人いるでしょ。あーいうのは大体、ウィスパー型の宿主なの。それが人間にとってインスピレーションになる場合もあるけど、大体は、気が滅入るようなことを耳元でささやく」
「何でそんな意地悪するの?」
「退屈だからでしょ」
青は船着場に打ち上げられた石ころを拾って海へ投げる。水面に浮いていたウミネコが慌てて飛び立つ。
「ヒマ潰しってこと?」
「うん、あと羨望も」
夜空に舞うウミネコを目で追いながら青は言った。
「精神寄生体が人間に?」
「自分にないものを求めるって点で人間と同じなの。あいつら精神体で不老不死なもんだから人間の死に憧れてる。だから、心が不安定な宿主をそそのかして道を誤らせたり、もっと酷くなると、独裁国家の政府主導部にクラスターを形成して、隣国との戦争を引き起こしたり。過去にはそれで滅んだ文明がいくつもあったって」
「待ってそれって完全、悪じゃん」
「うーん」と青は、ぼんやりを輝く月を見上げる。「それがクストゥデスの役目なんじゃないかって学者もいて」
「破滅へ導くことが?」
「破壊の後には創造があるでしょ。このサイクルのおかけで人は永遠に生き続けるんだって」
「ちょっと待って、どういうことか全然分かんないんだけど」
「人間の最大の特徴は知性だよね。で、それをどんどん上昇させていくとさ、いつか限界が来るの。てっぺんまで行くと後は下るのみ。それを過ぎると、どんな知性を持った生命体も遅かれ早かれ必ず絶滅しちゃうんだって」
「何で?」納得いかない。
「生きる目標を失う。人類規模の燃え尽き症候群てやつ?」
「それは誰が言ってんの?」
「公安お抱えの偉い学者だよ。シンギュラリティとかAIとか文明論とか研究してる。そのおっさん曰く、人類の『アブソルートスタティック』、知性の発展が止まる『絶対的静』を避けるには定期的に完成を防ぐ破壊的狂気が必要なんだって」
「ちょっと待って。権力者の耳元でささやいて文明を破滅させることが、人類の存続に必要って、完全な倒錯じゃない?」
そんなことを言うのはマッドサイエンティストに違いない。孤島で一人変な動物を作っていればいいと思う。
「巨視的に見たらそういう考えもあるってことで、実際の生活にそんな奴がいたらたまったもんじゃないでしょ。だから日本では公安総務部が調査を担ってる」
「あなたみたいな人が他にもいるってこと?」
「うん。今、東京はあいつらが増えてて、スタッフ急募中だよ」
渋谷と出勤中の電車、二回の遭遇を思い出す。
「何しに来てるの?」
「東京ってさ、人口も機能も資産も、人類史上、類を見ないほど集積されてんだって。その『バベルの塔』が崩壊するのをまた見たい、カタストロフ好きのクストゥデスが押し寄せてるんじゃないかって」
「災害を待ってるってこと?」
とことん嫌な奴らだ。悪夢を見た時の拒否反応は正しかったと思う。
「あと戦争ね。テロリストとかカルトとか反政府系組織に、破滅思想を先導するクラスターが発生しないよう宿主チェックしてる。それが見守り隊の仕事」
「それって本当に世界を守ってない?」
「そうでもないよ。世界なんてどーでもいいし。アタシの業務は内偵だから。街であいつらを見つけんでしょ? で、それを宿主データベースに照会して、初モノだったら三万三千円現金で貰える。昔は一匹十万出てたらしくて。増えてるから値下がりしたんだって」
「バイト代出るんだ」しかも結構な金額だ。
「歩合だけどね。一日渋谷にいて最高記録は四人、平日だとゼロの時も多いね。でさ、見守り隊やってると、こいつはどう考えてもヤバいだろって奴がいんの。宿主をどんどん追い込む超キモい系。そういうのはさ、本当はダメなんだけど、ボランティアで掃除してんだ」
「クストゥデスって不死身なんじゃ」
「アタシはイミミの技法で、自分が死にゆくリアルな夢を見れる。めっちゃくちゃ写実的だから、あいつらには現実と区別がつかない」
私の腕で確かに息絶えた青を思い出す。
「で、死んだと思って、ノコノコ入って来た瞬間、夢だったことを明かして、抗体でバリバリに噛み砕いてやんの」青は、右手の狐をパクパクと動かし声色を変える。
「キツネジャナイヨ ウサギダヨ」
「クストゥデスはどうなるの?」
「その宿主には二度と近づかなくなるね。死に憧れるっていっても自分がヤバいと思ったら切るんだし、所詮は、他人の死を覗き見したいだけなんだよな」
「月に変わってお仕置きか」輪河鈴が昔見ていたアニメを思い出す。
「一度、完璧に嵌めたことあってさ、その時は二十人の宿主クラスターが全員解放された。自慢したら、総務部の奴にめちゃくちゃ怒られたよ。わかんないけど、あいつら天然記念物的な感じで保護されてるみたい」
「ごめん、ちょっと待って」私は青の話を遮る。「いったん整理したいんだけど」
寄せては返す波の音が沈黙を埋める。
追い詰められたプロ棋士のように長考していると、青はおどけて言った。
「一曲歌おうか?」
「うん」私は上の空で返事する。
「じゃ、Aikoのカブトムシです」
青は意外といい声で、思考を妨げないBGMになった。可愛いし、お喋りも達者で、歌も上手い。やっぱり本当はユーチューバーなんじゃないかと思った。全部作り話でした。そんなオチを期待し、歌い終わるのを待って私は訊いた。
「それがさっき私が受けたドッキリテストだったてこと?」
「そうだよ」青は屈託なく頷き、右手のウサギが続いた。
「カブトムシハ アマイカオリニ サソワレナカッタネ」
「私をクストゥデスだと思ったのはいつ?」
自分の声は思ったより冷静で、別の誰かが喋っているようだった。
「宮下パークで宿主の追跡調査してたら、レイヤードからあいつらが出てきて、アンタ腰抜かしてさ。最初は、この人、視えてんなと思ったわけ」
「それってあの顔のこと?」
「アンタにはそう視えんだね」青は眉間に皺を寄せる。
「年齢も性別も人種もあらゆるタイプの人間を合わせて平均値を取ったような、ものすごく整った顔。それが酷い声で鳴く」
「人によって受容体が異なるから感じ方も違うんだけど、アンタには、あいつらが今まで宿主にしてきた人間の顔が重なって視えてるのかも。鳴き声は聞いたことないけど、もしもクストゥデス間でコミニュケーションを取ってたら大発見だわ」
ベビーカー事件をかいつまんで話すと、青は顎に手をあて、真剣な眼差しで海を見つめる。
「周りの受容体を持つ人間に、電波塔みたく怒りや悲しみを放射したのかな。宿主以外にも影響を与えられる新種かも。やっぱり集まることで、いろいろ変異が起こってるのかもしれない」
「でも、なんで私にそんなことがわかるの?」
青は右手でウサギを作りクルクル回す。
「アンタの感性がクストゥデス的ってことでしょ。アタシは視る方は大したことないから近づかないとダメなんだ」青は顔を寄せて目を閉じる。「こうするとさ、ウチナーでは『ウカミヌキ』って呼ぶんだけど、その人固有の“枝”が視えんの。アタシたちイミミはその流れから過去や未来を占う。アンタがどんなか視させてもらったら初めてのタイプでさ」
「あなたに私はどう映ってるの?」
「普通の人間は緑で、あいつらに憑かれると紫になる。けどアンタは接ぎ木だった」
「つぎき?」
「合体してる。緑が台木で、途中からはっきり紫だったよ」
閉じた瞼の下で青の瞳がキョロキョロと動く。
「それは今も?」
「いや、前回よりさらに進んでるね。緑と紫がマージして別の木になってる。順調に育ってるって感じだよ」
以前、担当医からアナムネーシスの話を聞いた時以上に、青の話は、私の混乱を説明する物語として適切な気がした。
「そっか」
私は覚悟を決めた。青は敏感にそれを察する。
「とりあえず、アンタに関して知ってること全部話そうか?」
「お願い」
「アタシは一か月くらい前から、行方不明になったクストゥデスを捜査してた。『ロメオ』ってやつ。発見されたのは一九八九年のミラノで、五十人規模のクラスターを形成してた」
「もしかしてシェイクスピアからつけたのかな」精神寄生体にしてはロマンチックな名前だと思ったが、青は興味がないらしくスルーする。
「アタシがロメオを調査したのは日本に来てすぐ姿を消したから。それで総務部に『また青が私刑を行ったんじゃないか』って言い出す奴がいて」
「前科あるもんね」
あの時、青の身体に侵入していたらどうなっていただろうと考えたが、うまく想像できなかった。
「今回は完全濡れ衣だよ。アタシは疑惑を晴らそうと思いロメオが作ったクラスターを当たってた。その一人がアンタがあの時一緒にいたメガネのオジサン」
「ライターさん」黒縁眼鏡の丸顔が浮かんだ。彼が悪いわけではない。しかしこの混乱をもたらした張本人だと思うと腹がたった。
「公安の資料だと五年間ミラノに住んでて、コロナの前に日本へ帰ってきた。あのメガネが、ロメオ東京進出の一歩だとアタシはにらんでる」
「建物から出て来たのは?」
「あいつはあの辺によくいる古株だよ。昔から渋谷の街が好きでさ。アンタは腰抜かしてたけど人畜無害。単なるツーリスト。でも、電車の奴はやばそうだから見回っとくわ」
青はまた狩りをするつもりらしい。
「クストゥデスって宿主はどうやって増やすの?」
「固体によってバラツキがあるんだけど、基本は受容体が適合した上で、相手の名前を知ってて、身体に触れたことがあって、あと会話したことがあるとか、そんな感じかな」
「それだけ?」
それならライターの他にも条件が合う人はたくさんいる。
「受容体が合うって条件が結構シビアだから。あ、死に際は別ね。精神的抗体が弱まって条件なしに侵入できる。だからあいつら病院好きでさ。誰かが亡くなりそうになるでしょ。そしたらそれを嗅ぎつけて寄ってくんの。人はその気配を感じて勝手に天使や死神だ幽霊だと思ってるわけ」
入院中に出くわさなくてよかった。個室を選んでくれた母に感謝した。
「クストゥデスが頭に入ると、宿主の記憶はどうなるの?」
一番気になることだった。断片的に思い出してはいるが、未だ事故前の数日間は謎に包まれている。
「あいつら次第かな。普通は影響ないけど、行儀が悪い奴なら記憶をいじることもあるみたい。けどそれが限界で、身体を乗っ取るとかは多分、無理」
ライターと出会った覚えがないから、宿主になって数日後に融合が起きたということか。重い宣告だったが、同じくらい納得感もあった。
「クストゥデスと人間が一つになることはあるの?」
「アタシは初めて。だから、最初はタチが悪い奴だと思った。緑と紫が絡み付いてジャンプしそうもなかったし、宿主の肉体を乗っ取る新種かなと。で、呼び出して、テストさせてもらったわけ。結果、アンタは、アタシが死んでくのを見ても全く興味を示さなかった。よって、アタシのボランティア活動はこれで終わり。宿主を見つけたら報告義務があんだけど、アタシはあなたのこと人間だと思うから黙っとく。周りにも、アンタのことは見逃すように言っとくわ」
「濡れ衣を晴らせないね」自分にクストゥデスという意識はなかったが、申し訳ない気もした。
「別にいいよ。ロメオの件はアタシがやったって雰囲気になってっから。このまま事を荒立てなけりゃ、証拠もないし大丈夫でしょ」青は面倒臭そうに手を振る。
「最後にもう一ついい?」
「ここ出たら、この話は二度としないから、なんでも訊いときなよ」
「私は何者なんだろ」目覚めた時からずっと心にある疑問だった。
「わかんない、けどアタシの印象でいいなら」青は再び目を閉じる。「新しい生命って感じがする。輪河鈴とロメオのそれぞれから記憶と思考を受け継いだ、子供のような」
駐車場に戻ると店の明かりは消えていた。青が生垣に隠した携帯を見つけ、電源を入れる。十件の着信があった。全て編集長からだった。すぐに連絡し事情を話す。携帯を置いて、青と追いかけっこしてたら、二人して堤防から落っこち、上がるのに三時間がかかった。かなり無理な説明だったが、「君たちは小学生か」と大きなため息をついて許してくれた。
帰りは助手席に青が座り、私は少し狭い後部座席ですぐ眠りについた。
◆
初めて、夢を見た。
人類を見守る中で、ロメオは憧れを抱く。始まりは死への興味だった。そこから幾千万もの生涯を目にし、人が放つ輝きに心を奪われていく。そして、時として人間が燃えるように煌めくのは、終わりを持つからという認識に至る。憧憬はいつしか渇望にかわり、ロメオは自らも、始まりとピリオドのある物語を紡ぎたいと願うようになった。
そんな時、新しい宿と出会った。ロメオのために設えたような空間には、立派な玉座が置かれ、その部屋にいると厄介な夢からも守られた。ロメオは移動をやめると、椅子に腰掛けて、人間のように自らの物語を考え始めた。
二人が出会い、結ばれて、終わる。そんなストーリーを選んだのは、ロメオが、かつて自身に付けられた名前の由来となる文人を宿主にしていたことも影響していた。
宿主は女性だった。彼女もまた自らの物語を持っていた。王のために築いた部屋を、王と壊す。 部屋の壁にはテーマであろう言葉が深く刻み込まれていた。
「主よ、わたしを平和の器としてお使いください。 与えることで私たちは受け取り、 死ぬことにより、私たちは永遠の命に生まれ変わる」
読むと甘い香りが広がった。ロメオは自らの半身に出会ったと確信した。話しかけると彼女はすぐ反応した。部屋を囲う硬い殻は外部の刺激を遮断しており、内側から語りかけるロメオの声はダイレクトに響いた。
「もしあなたがそれを望むならともに行きましょう」
「あなたを、ずっと待っていた」
それ以上の言葉は必要なかった。二人は来たるべき日に備えた。
ロメオは出会いから終わりまで、彼女と過ごした輝くべき瞬間をまとめ、部屋の中央深くに埋めた。言うなればそれは、ロメオの書物だった。隠すことで物語は力を持つ。謎は人を惹きつける。ロメオは自分たちのストーリーが誰かに読まれるのを願った。
そうして、二人はホームから飛んだ。
線路の上で意識を失う直前、ロメオは彼女の身体を仰向けに寝かせた。
列車の警笛とブレーキ音が響き、器は砕け散った。彼女とロメオは手を取り合い、暗いところへ堕ちていく。これが死か。ロメオは思った。
──深淵で二人は境目を失い、あらゆる全てと一つになる
ロメオが最後のピリオドを打とうとしたその時、あらかじめ決められていたかのように奇跡は起きた。
両者の受容体が過剰に同調したことで、激烈なエネルギーが発生。彼女の記憶や神経繊維がロメオの精神エネルギーと非可逆的に再結合し、燃える塊になって、闇から光の方へ駆け登った。
世界に生まれる時、誰もが経験するたった一度の奇跡。魂の創生。
輪河鈴の肉体の上で、回送列車の車輪に付いたブレーキパッドが、新たな誕生を祝福する如く、盛大な火花を散らした。
目が覚めたら、私は彼らの物語を書くだろう。それが自分に託された役割だから。